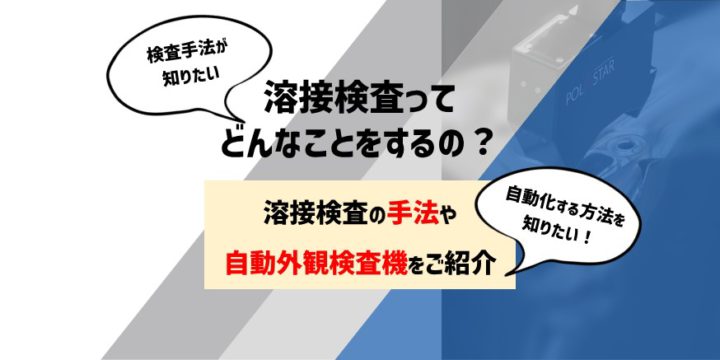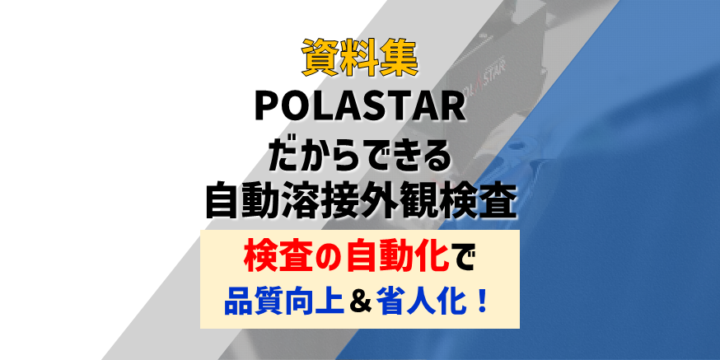MAG溶接とは?特徴と品質管理のポイント|自動化と検査精度向上を目指すあなたへ
- HOME
- ブログ
- 【POLASTAR-三次元計測】
- MAG溶接とは?特徴と品質管理のポイント|自動化と検査精度向上を目指すあなたへ
「NG品を次工程へ流さない」
品質保証部門で目視検査を担当されている方にとって、日々のプレッシャーは相当なものではないでしょうか?
自動車部品の溶接には、さまざまなアーク溶接法が使われていますが、中でもMAG溶接は大量生産に適しており、多くの現場で採用されています。この記事では、MAG溶接の基礎を振り返りつつ、品質管理の観点から注意すべきポイントを解説します。


CONTENTS
MAG溶接とは?
MAG(Metal Active Gas)溶接は、炭酸ガスや混合ガスといった「活性ガス」を使用するアーク溶接法のひとつです。鉄鋼材の溶接に適しており、溶接ロボットとの親和性も高いことから、自動車部品の量産ラインで広く利用されています。
MAG溶接の特徴
- 自動化に最適で、ロボット溶接と相性が良い
- 高い生産性:連続的な溶接が可能
- スパッタが多く発生しやすい傾向あり
スピードと効率に優れる一方、品質の安定化や外観不良の防止には注意が必要です。
品質保証の立場から見るMAG溶接のリスクと対策
MAG溶接では、以下のような不具合が発生するリスクがあります。
| 不具合の種類 | 主なNG理由 | 品質・生産上の影響 |
|---|---|---|
| スパッタ付着 | 製品の見た目が悪く、外観検査で不合格となる。後工程で異物として影響する恐れも。 | – お客様クレーム(見た目) – 塗装・コーティング工程での不具合 – スパッタ除去の工数増加 |
| ビードの蛇行やムラ | 規格通りの位置・幅・高さでビードが形成されていないため、強度不足や設計不適合のリスクがある。 | – 設計強度を満たさない恐れ – 組立不良や干渉が発生 – 見た目の品質も低下 |
| ガス孔 (ブローホール) |
溶接内部に空洞(気泡)が残ってしまい、内部欠陥として強度が不安定に。 | – 疲労や応力集中による破断の原因に – 非破壊検査でのNG率上昇 – 耐久性の劣化 |
| 溶け込み不足 | 母材へのアーク熱が不十分で、接合が浅く強度不足になる。 | – 荷重に耐えられず破断リスク – 動的負荷や振動環境に弱い – 安全性への重大な影響 |
| 過剰溶け込み | 熱入力が過大で母材が深く溶け込みすぎ、溶接変形や裏面への影響が出る。 | – 形状変化による組立不良 – 板厚を損なう可能性 – 品質規格外としてNG判定 |
品質確保のチェックポイント
| チェック項目 | 確認ポイント | 管理の目的 |
|---|---|---|
| 溶接条件の安定性 | 設定値にブレがないか、ロボットや設備の動作に変化がないかモニタリング | アークの安定、ビードの形状安定、 |
| トーチ角度とガス流量の確認 | 溶接ロボットの動きとガス流量の管理 | ガス孔の防止、アークの乱れを回避、酸化防止 |
| ビード形状 | ビード幅、高さ、位置が設計通りか定期的な検査 | 外観、強度、組立時の干渉防止 |
検査精度を高めるには?検査工程の自動化がカギ
人の目に頼る検査には限界があり、作業者によるバラツキや見逃しも課題の一つ。そこで注目されているのが、溶接ビードの自動検査システムです。
安定した判定基準と高速処理により、検査の標準化・見逃しの削減・トレーサビリティ強化が可能になります。
溶接ビードの自動検査を実現する「POLASTAR(ポーラスター)」のご紹介
コアテックが提供する「POLASTAR」は、3Dカメラとロボットを組み合わせた溶接ビード自動検査システムです。目視検査に代わって、より高精度かつ安定した検査を実現し、品質保証部門の業務負荷を大幅に軽減します。
POLASTARの特長
✔ 3Dカメラでビード形状を高精度にスキャン
✔ 判定基準を数値化し、検査の標準化を実現
✔ ロボットアームで複数箇所を自動スキャン
✔ NG判定箇所の位置・画像データを記録し、トレーサビリティも確保
✔ 現場の溶接ロボットと連携し、インライン検査にも対応可能

まとめ
MAG溶接は量産工程において不可欠な技術ですが、その分、品質検査には高い精度と安定性が求められます。「人の目に頼る検査」から一歩進み、自動化による安定品質と作業効率化を目指しませんか?POLASTARは、そんな品質保証部門の新たな検査スタンダードになるソリューションです。

2025.12.08
溶接とは?溶接の種類とほかの接合方法との比較
この記事では、溶接の基本的な定義と、溶接方法の種類を紹介しています。アーク溶接、MIG溶接、TIG溶接などの手法が取り上げられ、それぞれの特徴や用途について解説。また、溶接とリベット接合やボルト接合、接着剤接合などの他の接合方法との比較も行い、最適な方法を選ぶための指針を示しています。…